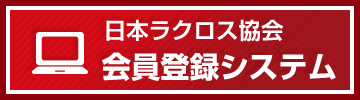ご挨拶
Lacrosse Makes Friends.
この日本ラクロス協会(JLA)のスローガンが、アジアや世界のラクロスコミュニティに広がり、ソーシャルインパクトを持ち始めています。これは、太平洋戦争下、米国収容所で捕虜の経験を持つ日系3 世のNorio Endoさん(JLA の最初のリーダー)の言葉です。
「ラクロスの若い世代の国境を超えた友人関係は一生もので、それぞれが各国でリーダーになれば、世界中のあらゆる紛争は回避・解決できる」
Endo さんは、米国ジョンズホプキンス大学、海軍士官学校を経て、トップガンパイロットになりました。ベトナム戦争で友を失い、1980 年代の日米経済摩擦の中でビジネスパーソンとして苦悩した彼は、” 平和” と” 異文化コミュニケーション” の大切さを人一倍理解していました。そして、その社会課題の解決を、日本の若い世代とカレッジスポーツ・ラクロスに託しました。
「パイロットにはブレーキがない。止まることも、バックすることもできない。ただ、ひたすら前へ、未来へ進むしかない」
「ラクロス文化を作っていくのはオトナ達ではなく、グラウンドの現場で、遊び心をもつ学生が、自ら考えて自由なラクロスを担っていく」
JLA が、大会や組織運営を学生・社会人ボランティアに委ね続けているのは、このEndo さんの未来志向DNA が原点になっています。JLAには、スポーツの枠を超えた想いと生い立ちがあります。
ラクロスには、どんな国の人たちとも、互いを個人として尊重し、スティック一本で、新しい出会いと文化を発見するワクワク感があります。そして、それは国内の異なる地区、チーム、世代、ファンでも同じです。
この、Lacrosse Makes Friendsに込められた情熱を、ラクロスコミュニティの方々と共有し、さらには、ファンの皆さん、ジュニア世代、アジアや世界の新しい私たちの仲間へ伝え広げていきましょう。
公益社団法人日本ラクロス協会 理事会